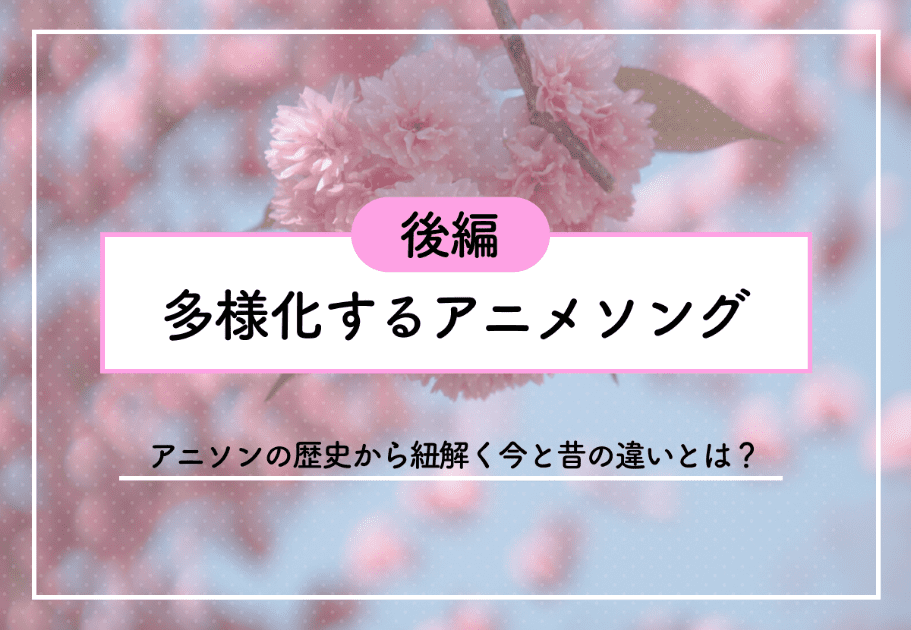アニメソング(アニソン)がどのような歴史を辿り生まれたのか「【前編】多様化するアニメソング。アニソンの歴史から紐解く今と昔の違いとは?」で説明しました。
「後編」では、アニソンの歴史の2000年代から現在に至るまでを解説しつつ、多様性溢れるアニソンが今どうなっているのかについて紹介します。
この辺りの時代のアニソンだと、聞き知っている人も多いのではないでしょうか。
ぜひ、自分の好みのアニソンを思い浮かべながら御覧ください。
目次
アニメソング(アニソン)の歴史
前編を振り返ると、当初はアニソンではなく童謡であることを説明しました。
しかし、次第に時代の背景に合わせて泥臭さや雰囲気を意識したタイアップ曲が増えていきました。
後編ではそれがどのような変化を遂げてきたのか、アニソンの立ち位置も踏まえながら解説していきます。
【2000年代】タイアップと非タイアップの二極化
2000年以降のアニソンは90年代に比べてタイアップ曲と非タイアップ曲の二極化が挙げられます。
この頃になるとアニメの視聴率が激減。これには少子化などが要因とされており、視聴率が低迷する中で売上をどのように伸ばすかというビジネス展開を練ることが重要視されるようになりました。
それに伴い年間のアニメタイトルが乱発するようになり、売上の減少などによってアニメの本数は増えたものの長期的なアニメが少なくなっていきました。
また、90年代のアニメを観て育ったファン層、いわゆるオタク層が増加したことにより、アニメの内容もファンに合わせた作品を制作するために模索する日々が続きました。
アニメの変化に合わせるようにアニソンにも変化が表れました。90年代に流行したオシャレさを追求したタイアップ曲は、アニメファンの変化によってアニメの世界観に沿った内容の歌詞などにシフトチェンジ。
しかし、バンドなどはすでに自身の世界観が確立されており、ファンもそんなバンドを支持しています。アニメの世界観とアーティストの世界観を合わせる必要があり、その結果アーティストの個性が強いタイアップ曲が増えていったようです。
そんな中、非タイアップ曲と言われる声優やアニソン歌手による曲が主題歌を担当するようになり、これらの曲はアニメファンを意識した当時の「萌え系」や「燃え系」に該当します。
オタクに合わせたビジネス展開が行われ、声優やアニソン歌手に特化したイベントの数が増加。とくにアニソン歌手および声優として活躍している水樹奈々さんの登場は大きな変化を与えたのではないでしょうか。
水樹奈々さんも積極的なライブ活動を展開し、ついには声優として初の紅白歌合戦に出場するという快挙を成し遂げたのです。これに追従するようにアニソン歌手も紅白に出場する機会が増えていきました。
その他にも平野綾、田村ゆかり、茅原実里、川田まみ、KOTOKO、いとうかなこ、坂本真綾といった声優やアニソン歌手の活躍も大きく、90年代はタイアップ一色とまで言われる程のアニソンでしたが、こういった声優やアニソン歌手の活躍もあり、アニメの主題歌はその作品に応じて二極化されるようになりました。
【2010年~】キャラソンやアニソン歌手の活躍
2010年以降では、アニソン歌手やキャラクターソング(キャラソン)の活躍が目立つようになります。
アニメも歌を主体とした世界観が作られるようになり、代表的なのが『THE iDOLM@STER』『うたのプリンスさまっ♪』『ラブライブ!』といったアイドルアニメです。
アニメ内での声優が実際にステージで歌うようになり、関連グッズなどが多数販売されました。
アイドルアニメに限らず歌によるバトルアニメ(戦姫絶唱シンフォギア)やロボットアニメ(マクロスΔ)など、アニメと歌の関連性が強くなる傾向にありました。
また、アニソン歌手では水樹奈々さんを筆頭に女性アーティストが続々と登場。鈴木このみ、LiSA、May’n、藍井エイル、黒崎真音といった新人アニソン歌手にスポットが当てられるようになりました。
これによりアニソン歌手のライブやグッズ展開が急激に増加。紅白歌合戦に出場するだけでなく日本武道館での大型ライブなど、アニメだけでなくアーティスト個人としての活躍の場が増えてきました。
曲調自体はそれほど大きな変化はありませんが、アニソンとロックが密接したものが増えてきた傾向にあります。テレビアニメ『Angel Beats!』では、アニメ内のロックバンドのヴォーカルをデビュー前のLiSAさんが実際に担当していたこともありました。
少し前ではあまり考えられないテレビ出演やライブの開催が当たり前となり、アニメを知らない一般層にも知られるようになったことで、アニソン歌手と一般アーティストとの溝がなくなりつつあります。
多様化するアニメ・アニソンの変化
現在、国内で放送されるテレビアニメというのは、2000年代中頃から年間200本という数字にまで達しています。
2000年以前のアニメ本数というのは、50~100本程度の数字だったことを考えると驚異的な数値となっています。
これにはアニメを視聴するファン層の変化やアニメを制作するスタジオの増加など、様々な要因が挙げられます。
しかし、こういったアニメが乱立する現在では、それだけ業界内の競争が激しくなり、アニメとそれに関連するアニソンやグッズ、イベントなどでは多様性が求められるようになりました。
上記のアニソンの歴史でも触れていますが、現在のアニメ業界がどのような変化を起こし、アニソンにも影響を与えているのかを簡単に紹介していきます。
アニメとアニソンは相互関係にある
現在のアニメとアニソンは相互関係にあります。
これは、多くの人がアニメを目的にしてアニソンに入ることがほとんどだからです。
アニメを観て、そして約90秒という主題歌を聴く。そうすることでどれだけの情報量がその曲に込められているかがわかるのではないでしょうか。
雰囲気だけだった90年代の曲とは違い、昨今のアニソンはアニメの内容を重視した歌詞がほとんどです。
それらが合致することによってファンに深く根付き、ライブでその主題歌が流れれば、ファンの熱狂も倍増するでしょう。
これがアニメだけではそうはなりません。現在のアニメは1クールでの放送が当たり前となっており、短いアニメで完璧にファンの心を掴むというのは難しくなっています。
また、アニソンだけでもファンを盛り上げることは難しいでしょう。特定のアニソンやアーティストの音楽が好きというファンでなければ、初見で聴いた人にはなかなか届きません。
アニメとアニソンが相互関係にあることはもはや当たり前となっており、ふたつが寄り添うことはこれからも非常に重要な要素となっています。
選択肢の増加によりヒット作が出にくい
近年、アニメ作品が格段に増えたことを説明しましたが、これによって声優やアニソン歌手の活躍の場が増えたことは確かでしょう。
しかし同時に、現在のアニメ業界では一回のヒットでは成功とは言えなくなりました。
アニメ本数が少なかった2000年以前は、ターゲットが絞られ、視聴者側の選択肢も少なく済みました。
ですが、現在の多様性溢れるアニメ業界は、似たような作品が多く出回っています。それによって選択する視聴者側をしっかりと獲得することが難しくなり、業界全体を震わせるようなヒット作でない限り、成功とは呼べなくなっているのが現状です。
これは起用される声優やアニソン歌手も同じです。前の項目でアニメとアニソンは相互関係にあるとありますが、固定のアーティストのファンでない限り、業界内で話題を集めることはできません。
現在の1クールがほとんどのアニメで成功を収めるには、そのヒット作に乗らなければ難しくなっています。
とくに似たような作品が乱立する現在では、その中でどのようにしてクセを出すかが重要となっており、一時的な人気だけでは安心できない現状になりつつあります。
ビジネス形態の変化によるアニソンの変化
アニメソングの評論家と知られる冨田明宏さんは、アニメのビジネス形態は年々変わりつつあると語っています。
アニメが年間で200本を超える本数が放送されている現在では、ヒット作というのは年間5本あるかないかだそうです。
これがどのようなことを引き起こすかというと、アニメそのものが消失する可能性もあるということです。パッケージとしてリリースを重ねてもヒットしなければ赤字となってしまいます。
そのため現在ではNetflixやアマゾンプライムなどを用いたアニメ配信が増え、アニメの形態が変わりつつあります。
これにはアニソンにも大きく影響し、配信を意識したアニメが主流となれば、その音楽性や起用するアーティスト、言語なども関わってきます。
一部では主題歌を挿入歌として使用するという考えもあるようです。
先の項目で主題歌はアニメと相互関係にあるとしています。主題歌そのものがなくなることはないでしょうが、その立ち位置は今後の流れによっては大きく変化をするかもしれません。
時代によって変化していく
童謡から始まったアニメ音楽は、その年代によって様々な変化を遂げてきました。
現在主流となっているアニソン歌手による主題歌も、今後大きく変化をするかもしれません。
ビジネス的な面もあれば、ファン層の変化など、その要因はひとつではないでしょう。
それがどのような形でファンに届けられるのか、アニメファンにとっては気になるところでしょう。
もしこの記事を読んで気になった人は、自分が好きだったアニメやアニソン歌手を今と比べてみて、どのように変化をするのだろうと予測してみるのもひとつの楽しみかもしれません。
それでは、ここまでご覧いただきありがとうございます。
![カルチャ[Cal-cha]](https://ticketjam.jp/magazine/wp-content/uploads/2021/04/logo-v2.png)