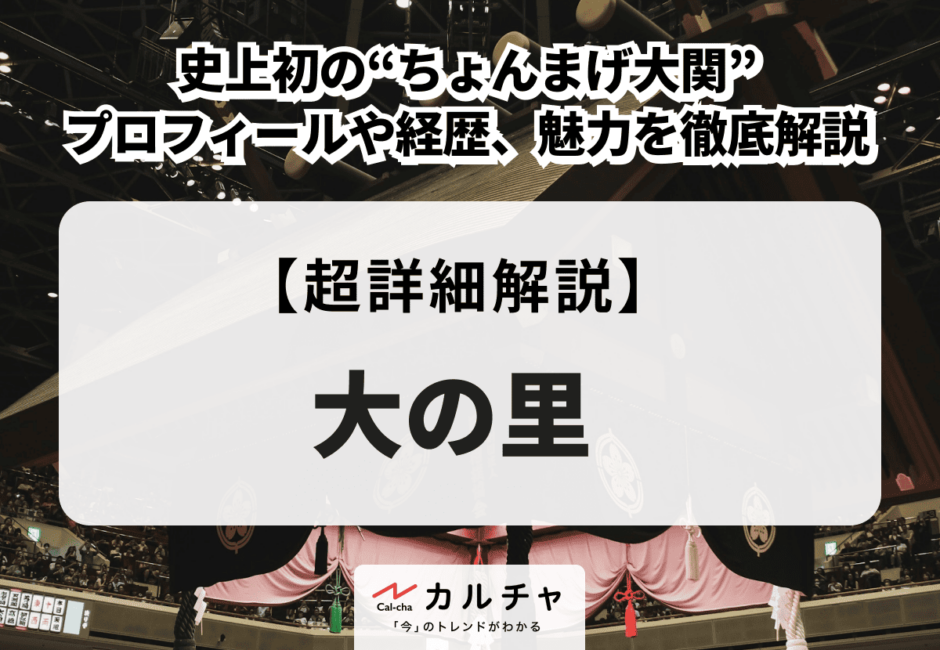目次
大の里、何が凄い?
“史上最速・大関” “史上初のちょんまげ大関“などという言葉が飛び交い、注目を集める大の里。
入幕から築き上げた数々の功績の中から、大の里の凄さがより良く分かる「史上初」の記録を紹介します。
- 新入幕から5場所連続で三賞受賞
- 新入幕から大関昇進までのすべての場所で三賞受賞
- 新入幕の年に2回以上の優勝
- 関脇と小結の地位で優勝
- 新入幕の年に大関昇進
- 入門から負け越しなしでの大関昇進
- 初土俵から所要9場所で史上最速の大関昇進
- ちょんまげ姿の大関
大相撲は、横綱を筆頭に、大関・関脇・小結の三役、そして平幕 (前頭) の力士までを「幕内力士」と呼び、幕内力士に上がることを「入幕」と言います。
「幕内力士」の下には、十両・幕下・三段目・序二段・序ノ口の6つの階層がありますが、大の里は学生時代に好成績を上げたことで幕下で初土俵を踏んだことが、スピード出世となった一つ目の要因です。
さらに、幕下での初土俵から4場所で入幕し、史上最速となる初土俵からわずか7場所で幕内最高優勝を飾りました。
また、入幕から負け越しなしという好成績で、大関昇進の目安とされる「直近3場所合計33勝」にも到達し、わずか1年半前までは大学生だった大の里は、史上最速となる初土俵から9場所で大関へ昇進しました。
そんな、異例のスピード出世の象徴が、まさに大の里のヘアスタイル。
十両以上の力士は「大銀杏」を結うことが許されていますが、大の里はあまりのスピード出世のために新入幕場所でも丁髷 (ちょんまげ)さえ結えずに、“ざんばら髪”が大きな話題になりました。
新三役・小結として迎えた令和六年五月場所で初めて“ちょんまげ”を披露しましたが、それからわずか3場所で大関へ昇進したため、極めて異例の“ちょんまげ大関”が誕生することになったのです。
大の里の取り口・得意技を解説
得意技を解説
- 突き :相手の上体を手の平で、強く叩くように突っ張っていく技
- 押し :相手の上体を手の平で、強く押し続ける技
- 右四つ:自分の右手を、相手の左脇の下に差して組み合う体勢
- 寄り :相手の廻しを取って、押し込むことを指す技 (廻しを取らない場合が「押し」)
- 押し出し…43%
- 寄り切り…25%
- 叩き込み… 9%
- その他 …23%
取り口や強みを解説
大の里は、なんと言っても身長192cm、体重182kgの力士として恵まれた体格、そして鋭い出足と馬力を活かし、右四つで前に出ていく相撲が武器。
さらに、立ち合いから“諸手突き (両手で突くこと)”で一気に相手を押し出すなど強烈な突っ張りや押しも得意で、体が大きく力が強い上に腕が長い大の里の突っ張りの威力は、専門家からも「相当なもの」と表現されるほど圧巻です。
一方で、相手の動きも見極めるどっしりとした取り口と、巨体ながら俊敏さも持ち味。
令和六年九月場所の十日目で対戦した、元大関・関脇の霧島が立ち合い左に動くも、体勢を崩されることなく正面から寄り切る抜群の対応力も発揮しました。
平幕だった入幕から2場所は体格を生かした力技の取り組みが目立ったものの、小結・関脇へと昇進するにつれて繊細な技術力も際立つようになり、成長の著しさも大の里の相撲の大きな魅力となっています。
史上最速の大関昇進を果たし、角界を盛り上げる期待の“ちょんまげ大関”
令和六年一月場所、まさに“彗星”のごとく大相撲界に登場するや否や、新入幕とは思えない安定感のある力強い取り組みで勝ち星を重ねて、圧倒的な存在感を放った“ざんばら髪”の若き力士・大の里。
新入幕から、5場所連続での勝ち越しと三賞受賞、2度の最高優勝という余りにも華々しい結果を残して、初土俵からわずか9場所という史上最速での大関昇進も果たしました。
怒涛の活躍で輝かしい記録を次々と打ち立てながら、先輩力士たちを押しのけるかのような勢いで“ちょんまげ大関”に昇進し、角界を盛り上げる期待の力士です。
![カルチャ[Cal-cha]](https://ticketjam.jp/magazine/wp-content/uploads/2021/04/logo-v2.png)